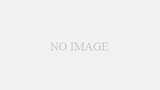12月も下旬を迎えました。年末の大掃除の季節ですが、皆さんはもう自宅の大掃除は済まされたでしょうか?
自分はまだ何も手をつけていませんが今年は風呂やトイレ、台所のシンクなどの水周りを中心に手を付けたいと思っています。普段は濡れるのが手間で少々雑にしか掃除できていませんでしたが、退職してせっかく時間もあるので少し気合を入れて手を出してみます。
というわけで、今回は風呂場掃除で最近知ったことをご紹介。
白いこびりつくアレ
風呂場掃除でやる気を削ぐ要因として風呂イスや蛇口、鑑などにつく白くこびりついたヨゴレ。あれ、なかなか落ちませんよね?
こすれば多少は削れますがやりすぎると本体のほうが傷つくし、どうしたものかと考えているうちに放置するようになってしまっていました。最近、お掃除系の配信者さんやYoutube動画などを見ていて知ったのですがどうやらあの白いヨゴレは「金属石鹸」と呼ばれていて石鹸成分と皮脂などが結合して固着するもののようです。
これは石鹸成分の脂肪酸イオンが、水道水成分や身体の汚れに含まれるカルシウムやマグネシウムと反応して脂肪酸カルシウムや脂肪酸マグネシウムになるからです。
水の中で溶解した界面活性剤分子は集合してミセルという分子集合体をつくります。
ミセルが汚れを包み込み、汚れを包み込んだままのミセルを水で洗い流すことで、界面活性剤は汚れを落としています。
ところが、そのミセルに汚れよりも先に金属が結合して金属石鹸になってしまうと、汚れをおとしたり、泡を作ったりする界面活性作用が失われてしまうのです。これを失活するといいます。
ですから、金属イオンをたくさん含む水を使うと石鹸の泡立ちが悪くなります。石鹸の原料として一般的な、オイルに含まれる脂肪酸(ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸など)はすべて金属石鹸を生成します。
参考:https://www.doctors-organic.com/soap/gousei/kinzoku.html
想像していた以上に厄介なシロモノのようです。
掃除は科学?
色々知らべていて面白いな、と思ったのが「掃除は科学で考えろ」という記事をいくつか見かけた時です。汚れを落としたいときは「その汚れが酸性orアルカリ性の性質をもっているか?」を知っておくと自然と掃除方法も見えてくるのだそう。
今回の場合は風呂イス等にこびりついた金属石鹸汚れですが、これは上の項目でも記載した通り「酸性汚れ」に該当するため、掃除用に用いる洗剤として適当なのは中性洗剤ではなくアルカリ性でした。
今まで掃除用としては食器洗いでよく使われるような中性洗剤や手洗い等で使う弱アルカリ性くらいしか使ってこなかったのでいまいちピンと来ていなかったのですが、とりあえずモノは試しにと薬局でクエン酸(粉末タイプ)を購入。
勢いのままクエン酸をお湯に溶かして100均で併せて購入したハケを用いて椅子にこびりついた白い汚れ部分に塗布。しばらく放置した後に適当なスポンジでこすってみました。
すると…

こんなにビッシリこびりついていた汚れが以下のようになりました。

いやー、驚きの結果です…。
まさかここまでごっそり落ちるとは思ってませんでした。風呂用洗剤などでどれだけこすっても中々落ちてくれなかった金属石鹸汚れがこうもあっさり拭えるとは。
ちなみに汚れの落ち方としては金属石鹸が剥がれるような感じではなく、塗布したクエン酸液によって柔らかくなっていたのか油汚れを拭き取るような感覚で拭い取るようにして落とすことができました。
完全に落ち切ったわけではないですが、今までと結果が違いすぎてかなりの満足感を得られています。
まとめ
今回は金属石鹸と汚れの性質について簡単に取り上げてみました。
掃除は科学で考える—知ってる人には当たり前のことだったかもしれませんが、私としては苦手とする掃除に対して良い知見を得ることができた体験でした。
今回使用したクエン酸は酸性ですが、アルカリ性の重曹なども薬局で安価で入手できるので今後を見据えて買い置きしておこうと思います。
それではまた次回~!